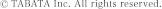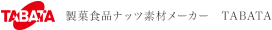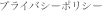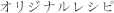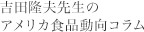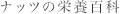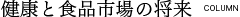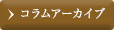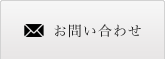まめ知識/まめ知識トップ/健康と食品市場の将来
2025.05.08
このコラムではこれまで健康と食品の関係を色々な面から考察してきた。世界の食品市場は人口増加と戦争や気候変動でこれまでにない世界的な不足をきたしている。今回は食品と健康の関係を中心に現在世界の食品市場の状況や傾向を考え、今後それらがどのように変化するかを考えてみた。
世界の食品生産は、穀類では20億トンとされており、世界全体の需要を満たす量としては充分にあるとされている。しかし、現在の食料供給は各国の経済的能力や政治的状況、戦争や紛争で、アンバランスな流通が生じている。国連の世界食糧プログラムによると、2023 年では3億3,000万人あまりの人々が食料の安定した供給を得られず栄養不足になっている地域があり、一部では飢餓に面しているところまである。ヨーロッパ諸国、北アメリカ、オーストラリア、日本を中心としたアジアの一部等では食料が現在のところ十分あるいは必要以上に供給されているが、アフリカや東南アジアや南米の一部などの低開発国を多く含んだ地域では食料供給の不安定な状態が続いている。日本は食料の6割ほどが外国から輸入され、食料自給率は低い。もし国内の気候変動によって農業生産が低下したり、食料を輸入している国々との間での紛争が起これば、食料の安定的な供給が脅かされるのは自明である。食品の安定供給はその国の人の健康にも関係する。つまり、食料の供給が不足し、国民が十分な食品を摂取できなくなると、健康状態も悪くなる。日本も第二次世界大戦後の十年間くらいは、十分な食品がなく、色々な健康面での問題が起こっていた。日本は経済力を回復させ、戦後の復興期を乗り越えて豊かな国になったので、現在では国民のほとんどが豊かな食生活を享受することができている。しかし、日本の食料自足率は30%くらいで、多くの食品供給を外国に依存している。その一方で食料調達の難易度は年々高まりをみせ、それに伴って価格は高騰し、中国などが世界市場を押さえつつある。日本はもっと食料供給の仕方を変えていかなくてはならないのではないだろうか。世界を見ると、他国と交戦中の国の多くは、食糧の供給がうまくいかず、国民の健康状態が悪い所が多い。また逆に、先進国における過剰な食品の供給は、食べ過ぎによる生活習慣病などの増加につながっている。こうした国では食育教育で健康的な食事の仕方を教えることが行われているが、その効果は限られており、生活習慣病特に糖尿病などが増えている。健康を維持するにはどのように食事をするのが大事であるかを考える必要がある。
最近の食品市場では健康と食品の関係が大きく注目されるようになってきており、食品業界もそれに対応する食品を販売しようとする傾向が強くなっている。そうした傾向と食と健康効能、さらに今後の動きなどについて書いてみることにする。
農水産物
農水産物は我々の基本的な食品であり、またこれらを使った加工食品が食品市場で多く販売されている。町のスーパーに行くと勿論農水産物は並んでいるが、最近では加工食品のほうが多く販売されている。生の農水産物を買って家庭で料理をして食べるほうが、より健康的であると言われているが、忙しい現代社会では料理をする時間が少なく、加工食品を中心に食べる人が増えている。これまで農産物は主に気候に強い、病虫害に強い、収量が高いなど農家の利益を図るための品種改良、さらに大きさ、見栄え、美味しさなど消費者によりアピールするための品種改良が行われてきた。食品の栄養成分は厚生労働省が発行している日本標準栄養成分表にまとめられており、それを使って栄養管理士などは、病院の患者や高齢者のために栄養のバランスがとれた食事メニューを作っている。 農産物は季節や土壌の状態によっても栄養分が変化するので、それに対応したデータが出されているものもあり、農作物によってはそれを考えに入れておく必要がある。昔から多くの農水産物が経験的に身体にいいと言われてきた。今ではより科学的な知識から健康との関係が論じられるようになってきた。柑橘類にはビタミンCが多く含まれ、ニンジンにはベータカロチン(体内でビタミンAに変化)が多く含まれている。また、キャベツには胃腸の健康を維持するビタミンU(メチルメチオニン)が含まれており、ブロッコリにはガンを予防すると言われているスルフォラフェンという成分が含まれている。ナッツ類も不飽和脂肪酸、オメガ-3-脂肪酸、ミネラルなどが豊富に含まれており健康にいいと言われている。水産物でもシジミには肝機能を改善し、疲労回復に効果があると言われているオルニチンが含まれており、そうした機能をうたってマーケッティングがされている製品もある。
農産物は季節や土壌の状態によっても栄養分が変化するので、それに対応したデータが出されているものもあり、農作物によってはそれを考えに入れておく必要がある。昔から多くの農水産物が経験的に身体にいいと言われてきた。今ではより科学的な知識から健康との関係が論じられるようになってきた。柑橘類にはビタミンCが多く含まれ、ニンジンにはベータカロチン(体内でビタミンAに変化)が多く含まれている。また、キャベツには胃腸の健康を維持するビタミンU(メチルメチオニン)が含まれており、ブロッコリにはガンを予防すると言われているスルフォラフェンという成分が含まれている。ナッツ類も不飽和脂肪酸、オメガ-3-脂肪酸、ミネラルなどが豊富に含まれており健康にいいと言われている。水産物でもシジミには肝機能を改善し、疲労回復に効果があると言われているオルニチンが含まれており、そうした機能をうたってマーケッティングがされている製品もある。
農水産物は我々の基本的な食品であり、またこれらを使った加工食品が食品市場で多く販売されている。町のスーパーに行くと勿論農水産物は並んでいるが、最近では加工食品のほうが多く販売されている。生の農水産物を買って家庭で料理をして食べるほうが、より健康的であると言われているが、忙しい現代社会では料理をする時間が少なく、加工食品を中心に食べる人が増えている。これまで農産物は主に気候に強い、病虫害に強い、収量が高いなど農家の利益を図るための品種改良、さらに大きさ、見栄え、美味しさなど消費者によりアピールするための品種改良が行われてきた。食品の栄養成分は厚生労働省が発行している日本標準栄養成分表にまとめられており、それを使って栄養管理士などは、病院の患者や高齢者のために栄養のバランスがとれた食事メニューを作っている。
 農産物は季節や土壌の状態によっても栄養分が変化するので、それに対応したデータが出されているものもあり、農作物によってはそれを考えに入れておく必要がある。昔から多くの農水産物が経験的に身体にいいと言われてきた。今ではより科学的な知識から健康との関係が論じられるようになってきた。柑橘類にはビタミンCが多く含まれ、ニンジンにはベータカロチン(体内でビタミンAに変化)が多く含まれている。また、キャベツには胃腸の健康を維持するビタミンU(メチルメチオニン)が含まれており、ブロッコリにはガンを予防すると言われているスルフォラフェンという成分が含まれている。ナッツ類も不飽和脂肪酸、オメガ-3-脂肪酸、ミネラルなどが豊富に含まれており健康にいいと言われている。水産物でもシジミには肝機能を改善し、疲労回復に効果があると言われているオルニチンが含まれており、そうした機能をうたってマーケッティングがされている製品もある。
農産物は季節や土壌の状態によっても栄養分が変化するので、それに対応したデータが出されているものもあり、農作物によってはそれを考えに入れておく必要がある。昔から多くの農水産物が経験的に身体にいいと言われてきた。今ではより科学的な知識から健康との関係が論じられるようになってきた。柑橘類にはビタミンCが多く含まれ、ニンジンにはベータカロチン(体内でビタミンAに変化)が多く含まれている。また、キャベツには胃腸の健康を維持するビタミンU(メチルメチオニン)が含まれており、ブロッコリにはガンを予防すると言われているスルフォラフェンという成分が含まれている。ナッツ類も不飽和脂肪酸、オメガ-3-脂肪酸、ミネラルなどが豊富に含まれており健康にいいと言われている。水産物でもシジミには肝機能を改善し、疲労回復に効果があると言われているオルニチンが含まれており、そうした機能をうたってマーケッティングがされている製品もある。
しかし、こうした野菜や果物のビタミンや機能性成分は料理の仕方次第では機能性成分が減ってしまうこともある。例えばブロッコリを茹ですぎると、グルコシノレートからスルフォラフェンが生成されるために必要となる酵素ミロシナーゼが分解されてしまうのでスルフォラフェンの量は非常に少なくなってしまう。最近では、さらに栄養価あるいは、健康に関係する成分を増やした品種改良がおこなわれている。 例えばトマトには抗酸化剤のリコピンが多く含まれているが、その含有量が通常種の2倍のトマトやカロテン量が3倍のミニトマトをはじめ、水溶性ペクチンが通常品種の2倍含まれているオクラ、アントシアニンが多く入ったからし菜、水菜、リーフレタスなどの葉野菜、本来であればリコピンが少量しか含まれていないはずのところその量を増幅させたニンジン、ルテインが通常品種の1.5倍含まれるホウレン草やビタミンCの多く含まれるピーマンなど次々と新たな品種の農作物が開発、販売されている。食品アレルギーは最近、食品の健康問題として大きな問題となっている。アレルゲンを減らしたあるいは無くした品種が開発できれば食品アレルギーへの心配が少なくなるし、消費者により健康的な食品を提供することもできる。こうしたアプローチで北海道大学、京都大学とパナソニックの研究グループが、アレルゲンたんぱく質をなくした大豆品種を遺伝子編集で開発している。従来の交配による品種改良法よりも遺伝子組換え、遺伝子編集技術で品種改良が速くできるが、日本では遺伝子組換えや遺伝子編集に対する反対が強いので、まだそうした方法で作った品種は販売されていない。日本政府は遺伝子編集については、他の生物の遺伝子を組込む遺伝子組換えとは異なり、その品種が元来持っている遺伝子を編集するだけであるので、従来の品種改良と同じように安全で、同等であるとしている。この問題は今後も議論がなされていくであろう。ともあれ、こうした栄養素や機能性成分の多く入った品種の農作物が市場に出れば、消費者にとってはより健康的な食品の選択肢が広がることになるので好ましいことと考えられる。
例えばトマトには抗酸化剤のリコピンが多く含まれているが、その含有量が通常種の2倍のトマトやカロテン量が3倍のミニトマトをはじめ、水溶性ペクチンが通常品種の2倍含まれているオクラ、アントシアニンが多く入ったからし菜、水菜、リーフレタスなどの葉野菜、本来であればリコピンが少量しか含まれていないはずのところその量を増幅させたニンジン、ルテインが通常品種の1.5倍含まれるホウレン草やビタミンCの多く含まれるピーマンなど次々と新たな品種の農作物が開発、販売されている。食品アレルギーは最近、食品の健康問題として大きな問題となっている。アレルゲンを減らしたあるいは無くした品種が開発できれば食品アレルギーへの心配が少なくなるし、消費者により健康的な食品を提供することもできる。こうしたアプローチで北海道大学、京都大学とパナソニックの研究グループが、アレルゲンたんぱく質をなくした大豆品種を遺伝子編集で開発している。従来の交配による品種改良法よりも遺伝子組換え、遺伝子編集技術で品種改良が速くできるが、日本では遺伝子組換えや遺伝子編集に対する反対が強いので、まだそうした方法で作った品種は販売されていない。日本政府は遺伝子編集については、他の生物の遺伝子を組込む遺伝子組換えとは異なり、その品種が元来持っている遺伝子を編集するだけであるので、従来の品種改良と同じように安全で、同等であるとしている。この問題は今後も議論がなされていくであろう。ともあれ、こうした栄養素や機能性成分の多く入った品種の農作物が市場に出れば、消費者にとってはより健康的な食品の選択肢が広がることになるので好ましいことと考えられる。
 例えばトマトには抗酸化剤のリコピンが多く含まれているが、その含有量が通常種の2倍のトマトやカロテン量が3倍のミニトマトをはじめ、水溶性ペクチンが通常品種の2倍含まれているオクラ、アントシアニンが多く入ったからし菜、水菜、リーフレタスなどの葉野菜、本来であればリコピンが少量しか含まれていないはずのところその量を増幅させたニンジン、ルテインが通常品種の1.5倍含まれるホウレン草やビタミンCの多く含まれるピーマンなど次々と新たな品種の農作物が開発、販売されている。食品アレルギーは最近、食品の健康問題として大きな問題となっている。アレルゲンを減らしたあるいは無くした品種が開発できれば食品アレルギーへの心配が少なくなるし、消費者により健康的な食品を提供することもできる。こうしたアプローチで北海道大学、京都大学とパナソニックの研究グループが、アレルゲンたんぱく質をなくした大豆品種を遺伝子編集で開発している。従来の交配による品種改良法よりも遺伝子組換え、遺伝子編集技術で品種改良が速くできるが、日本では遺伝子組換えや遺伝子編集に対する反対が強いので、まだそうした方法で作った品種は販売されていない。日本政府は遺伝子編集については、他の生物の遺伝子を組込む遺伝子組換えとは異なり、その品種が元来持っている遺伝子を編集するだけであるので、従来の品種改良と同じように安全で、同等であるとしている。この問題は今後も議論がなされていくであろう。ともあれ、こうした栄養素や機能性成分の多く入った品種の農作物が市場に出れば、消費者にとってはより健康的な食品の選択肢が広がることになるので好ましいことと考えられる。
例えばトマトには抗酸化剤のリコピンが多く含まれているが、その含有量が通常種の2倍のトマトやカロテン量が3倍のミニトマトをはじめ、水溶性ペクチンが通常品種の2倍含まれているオクラ、アントシアニンが多く入ったからし菜、水菜、リーフレタスなどの葉野菜、本来であればリコピンが少量しか含まれていないはずのところその量を増幅させたニンジン、ルテインが通常品種の1.5倍含まれるホウレン草やビタミンCの多く含まれるピーマンなど次々と新たな品種の農作物が開発、販売されている。食品アレルギーは最近、食品の健康問題として大きな問題となっている。アレルゲンを減らしたあるいは無くした品種が開発できれば食品アレルギーへの心配が少なくなるし、消費者により健康的な食品を提供することもできる。こうしたアプローチで北海道大学、京都大学とパナソニックの研究グループが、アレルゲンたんぱく質をなくした大豆品種を遺伝子編集で開発している。従来の交配による品種改良法よりも遺伝子組換え、遺伝子編集技術で品種改良が速くできるが、日本では遺伝子組換えや遺伝子編集に対する反対が強いので、まだそうした方法で作った品種は販売されていない。日本政府は遺伝子編集については、他の生物の遺伝子を組込む遺伝子組換えとは異なり、その品種が元来持っている遺伝子を編集するだけであるので、従来の品種改良と同じように安全で、同等であるとしている。この問題は今後も議論がなされていくであろう。ともあれ、こうした栄養素や機能性成分の多く入った品種の農作物が市場に出れば、消費者にとってはより健康的な食品の選択肢が広がることになるので好ましいことと考えられる。
機能性成分を添加した食品
加工食品では健康に寄与するビタミンや機能性成分を加えた機能性食品が多く販売されている。これは日本でも厚生労働省により保健機能食品として、機能性表示食品、栄養機能食品、特定保健用食品の3種類に制度化されている。 アメリカでは食品および食品成分で、科学的に健康効能に寄与することが示されているものには条件付きで表示が認可される。ヨーロッパでも同じような制度が運用されており、世界で食品と健康に対する関心が高まっている。この進歩は食品科学が発達し、食品や食品成分に関する研究が増えたことで、食品および食品成分と健康効能の関係が次第に明らかにされてきたことの成果である。しかしながらこうした関係を調べるには、個人間では毎日食べるものが異なり、さらに生活習慣などの多くの異なった因子があるため、非常に複雑である。動物を使った実験、医学的な臨床実験、多くの人を対象とした統計的データの疫学的分析などの方法を用いて、食品や食品成分と病気との関係が研究されているが、その関係が確実であることを証明することは難しい。ビタミンやミネラルについては人類の経験則や最近の研究により、欠乏することで病気や疾病が惹き起こされることが確認されている。例えば、ビタミンCと壊血病の関係、ビタミンAと目の病気、カルシウムと骨粗しょう症(最近ではマグネシウム、ビタミンDもなくてはならないことが示されている)、鉄分と血液の健康(貧血)、亜鉛と舌の機能や免疫機能などがある。しかし、一般には食品に含まれる成分などの健康効能の証明は非常に難しい。食品中に含まれる抗酸化剤であるポリフェノール、フルフォラフェン、カテキンやベータグルカンなどいくつかの成分はかなりの確実性でその機能性が示されている。これからも研究で健康効能が示されるものが増えていき、機能性成分を食品中に加えた加工食品がもっと増えていくであろう。気をつけなければならないのは、身体に必要であり、また健康効能を持っているビタミン、ミネラル、機能成分でも過剰に摂取すると逆に健康を害するものがあるので、適度に摂取することが肝要である。ここで機能性食品とは、本章で触れた機能性成分を添加した加工食品だけではなく、一般的な農水作物でも栄養素あるいは機能成分が多い物、またアレルゲン、非耐性物質、過剰摂取すると健康を害する成分(脂肪、砂糖、塩など)を取り除いた食品、さらにサプリメントも含めた総合的な食品群であることを指摘しておく。
アメリカでは食品および食品成分で、科学的に健康効能に寄与することが示されているものには条件付きで表示が認可される。ヨーロッパでも同じような制度が運用されており、世界で食品と健康に対する関心が高まっている。この進歩は食品科学が発達し、食品や食品成分に関する研究が増えたことで、食品および食品成分と健康効能の関係が次第に明らかにされてきたことの成果である。しかしながらこうした関係を調べるには、個人間では毎日食べるものが異なり、さらに生活習慣などの多くの異なった因子があるため、非常に複雑である。動物を使った実験、医学的な臨床実験、多くの人を対象とした統計的データの疫学的分析などの方法を用いて、食品や食品成分と病気との関係が研究されているが、その関係が確実であることを証明することは難しい。ビタミンやミネラルについては人類の経験則や最近の研究により、欠乏することで病気や疾病が惹き起こされることが確認されている。例えば、ビタミンCと壊血病の関係、ビタミンAと目の病気、カルシウムと骨粗しょう症(最近ではマグネシウム、ビタミンDもなくてはならないことが示されている)、鉄分と血液の健康(貧血)、亜鉛と舌の機能や免疫機能などがある。しかし、一般には食品に含まれる成分などの健康効能の証明は非常に難しい。食品中に含まれる抗酸化剤であるポリフェノール、フルフォラフェン、カテキンやベータグルカンなどいくつかの成分はかなりの確実性でその機能性が示されている。これからも研究で健康効能が示されるものが増えていき、機能性成分を食品中に加えた加工食品がもっと増えていくであろう。気をつけなければならないのは、身体に必要であり、また健康効能を持っているビタミン、ミネラル、機能成分でも過剰に摂取すると逆に健康を害するものがあるので、適度に摂取することが肝要である。ここで機能性食品とは、本章で触れた機能性成分を添加した加工食品だけではなく、一般的な農水作物でも栄養素あるいは機能成分が多い物、またアレルゲン、非耐性物質、過剰摂取すると健康を害する成分(脂肪、砂糖、塩など)を取り除いた食品、さらにサプリメントも含めた総合的な食品群であることを指摘しておく。
加工食品では健康に寄与するビタミンや機能性成分を加えた機能性食品が多く販売されている。これは日本でも厚生労働省により保健機能食品として、機能性表示食品、栄養機能食品、特定保健用食品の3種類に制度化されている。
 アメリカでは食品および食品成分で、科学的に健康効能に寄与することが示されているものには条件付きで表示が認可される。ヨーロッパでも同じような制度が運用されており、世界で食品と健康に対する関心が高まっている。この進歩は食品科学が発達し、食品や食品成分に関する研究が増えたことで、食品および食品成分と健康効能の関係が次第に明らかにされてきたことの成果である。しかしながらこうした関係を調べるには、個人間では毎日食べるものが異なり、さらに生活習慣などの多くの異なった因子があるため、非常に複雑である。動物を使った実験、医学的な臨床実験、多くの人を対象とした統計的データの疫学的分析などの方法を用いて、食品や食品成分と病気との関係が研究されているが、その関係が確実であることを証明することは難しい。ビタミンやミネラルについては人類の経験則や最近の研究により、欠乏することで病気や疾病が惹き起こされることが確認されている。例えば、ビタミンCと壊血病の関係、ビタミンAと目の病気、カルシウムと骨粗しょう症(最近ではマグネシウム、ビタミンDもなくてはならないことが示されている)、鉄分と血液の健康(貧血)、亜鉛と舌の機能や免疫機能などがある。しかし、一般には食品に含まれる成分などの健康効能の証明は非常に難しい。食品中に含まれる抗酸化剤であるポリフェノール、フルフォラフェン、カテキンやベータグルカンなどいくつかの成分はかなりの確実性でその機能性が示されている。これからも研究で健康効能が示されるものが増えていき、機能性成分を食品中に加えた加工食品がもっと増えていくであろう。気をつけなければならないのは、身体に必要であり、また健康効能を持っているビタミン、ミネラル、機能成分でも過剰に摂取すると逆に健康を害するものがあるので、適度に摂取することが肝要である。ここで機能性食品とは、本章で触れた機能性成分を添加した加工食品だけではなく、一般的な農水作物でも栄養素あるいは機能成分が多い物、またアレルゲン、非耐性物質、過剰摂取すると健康を害する成分(脂肪、砂糖、塩など)を取り除いた食品、さらにサプリメントも含めた総合的な食品群であることを指摘しておく。
アメリカでは食品および食品成分で、科学的に健康効能に寄与することが示されているものには条件付きで表示が認可される。ヨーロッパでも同じような制度が運用されており、世界で食品と健康に対する関心が高まっている。この進歩は食品科学が発達し、食品や食品成分に関する研究が増えたことで、食品および食品成分と健康効能の関係が次第に明らかにされてきたことの成果である。しかしながらこうした関係を調べるには、個人間では毎日食べるものが異なり、さらに生活習慣などの多くの異なった因子があるため、非常に複雑である。動物を使った実験、医学的な臨床実験、多くの人を対象とした統計的データの疫学的分析などの方法を用いて、食品や食品成分と病気との関係が研究されているが、その関係が確実であることを証明することは難しい。ビタミンやミネラルについては人類の経験則や最近の研究により、欠乏することで病気や疾病が惹き起こされることが確認されている。例えば、ビタミンCと壊血病の関係、ビタミンAと目の病気、カルシウムと骨粗しょう症(最近ではマグネシウム、ビタミンDもなくてはならないことが示されている)、鉄分と血液の健康(貧血)、亜鉛と舌の機能や免疫機能などがある。しかし、一般には食品に含まれる成分などの健康効能の証明は非常に難しい。食品中に含まれる抗酸化剤であるポリフェノール、フルフォラフェン、カテキンやベータグルカンなどいくつかの成分はかなりの確実性でその機能性が示されている。これからも研究で健康効能が示されるものが増えていき、機能性成分を食品中に加えた加工食品がもっと増えていくであろう。気をつけなければならないのは、身体に必要であり、また健康効能を持っているビタミン、ミネラル、機能成分でも過剰に摂取すると逆に健康を害するものがあるので、適度に摂取することが肝要である。ここで機能性食品とは、本章で触れた機能性成分を添加した加工食品だけではなく、一般的な農水作物でも栄養素あるいは機能成分が多い物、またアレルゲン、非耐性物質、過剰摂取すると健康を害する成分(脂肪、砂糖、塩など)を取り除いた食品、さらにサプリメントも含めた総合的な食品群であることを指摘しておく。
サプリメント
 サプリメントはビタミン、ミネラル、機能性成分を多く摂取できるように錠剤、カプセル、あるいは粉末製品にしたもので、市場には多くの製品がある。日本では日本栄養健康食品協会が機能性成分を製品にしたサプリメントに関する規格を決めている。ビタミン、ミネラル、機能性成分が食品に含まれる量は一般的には少ないし、また偏った食事をして不足していると感じた場合、あるいは特定の症状が起こった時は、サプリメントを利用して十分な量を摂取し欠乏症にならないようにする、あるいは特定の症状の改善をすることができるが、上に述べたように過剰摂取には気をつけなければならない。またサプリメントを処方薬と同時摂取すると、予期せぬ相互作用が起こる場合もある。サプリメントは医薬の代替え品ではなく、天然の原料から作られている食品だから安全であるという保証はない。サプリメントを摂取しすぎて肝臓をこわした人もいる。摂取する前に医師に相談をすることも大事である。最近ではサプリメントを従来の医薬と同じように処方する医師が増えてきている。新しい動きとしては、どのような病気に罹りやすい傾向があるかを遺伝子分析で同定し、個人のニーズにあったサプリメントを調合するサービスを提供するビジネスが始まっている。また腸内菌を分析し、その結果に応じて必要な腸内菌を加えたサプリメントを提供するビジネスもある。サプリメント市場は、アメリカでは成人の70%以上が何らかのサプリメントを摂取しており、大きな市場である。ヨーロッパでも高齢化と健康に対する意識増加で今後10% 近くの伸び率が期待されている。日本でも欧米ほどではないが、緩やかに市場は拡大している。
サプリメントはビタミン、ミネラル、機能性成分を多く摂取できるように錠剤、カプセル、あるいは粉末製品にしたもので、市場には多くの製品がある。日本では日本栄養健康食品協会が機能性成分を製品にしたサプリメントに関する規格を決めている。ビタミン、ミネラル、機能性成分が食品に含まれる量は一般的には少ないし、また偏った食事をして不足していると感じた場合、あるいは特定の症状が起こった時は、サプリメントを利用して十分な量を摂取し欠乏症にならないようにする、あるいは特定の症状の改善をすることができるが、上に述べたように過剰摂取には気をつけなければならない。またサプリメントを処方薬と同時摂取すると、予期せぬ相互作用が起こる場合もある。サプリメントは医薬の代替え品ではなく、天然の原料から作られている食品だから安全であるという保証はない。サプリメントを摂取しすぎて肝臓をこわした人もいる。摂取する前に医師に相談をすることも大事である。最近ではサプリメントを従来の医薬と同じように処方する医師が増えてきている。新しい動きとしては、どのような病気に罹りやすい傾向があるかを遺伝子分析で同定し、個人のニーズにあったサプリメントを調合するサービスを提供するビジネスが始まっている。また腸内菌を分析し、その結果に応じて必要な腸内菌を加えたサプリメントを提供するビジネスもある。サプリメント市場は、アメリカでは成人の70%以上が何らかのサプリメントを摂取しており、大きな市場である。ヨーロッパでも高齢化と健康に対する意識増加で今後10% 近くの伸び率が期待されている。日本でも欧米ほどではないが、緩やかに市場は拡大している。
 サプリメントはビタミン、ミネラル、機能性成分を多く摂取できるように錠剤、カプセル、あるいは粉末製品にしたもので、市場には多くの製品がある。日本では日本栄養健康食品協会が機能性成分を製品にしたサプリメントに関する規格を決めている。ビタミン、ミネラル、機能性成分が食品に含まれる量は一般的には少ないし、また偏った食事をして不足していると感じた場合、あるいは特定の症状が起こった時は、サプリメントを利用して十分な量を摂取し欠乏症にならないようにする、あるいは特定の症状の改善をすることができるが、上に述べたように過剰摂取には気をつけなければならない。またサプリメントを処方薬と同時摂取すると、予期せぬ相互作用が起こる場合もある。サプリメントは医薬の代替え品ではなく、天然の原料から作られている食品だから安全であるという保証はない。サプリメントを摂取しすぎて肝臓をこわした人もいる。摂取する前に医師に相談をすることも大事である。最近ではサプリメントを従来の医薬と同じように処方する医師が増えてきている。新しい動きとしては、どのような病気に罹りやすい傾向があるかを遺伝子分析で同定し、個人のニーズにあったサプリメントを調合するサービスを提供するビジネスが始まっている。また腸内菌を分析し、その結果に応じて必要な腸内菌を加えたサプリメントを提供するビジネスもある。サプリメント市場は、アメリカでは成人の70%以上が何らかのサプリメントを摂取しており、大きな市場である。ヨーロッパでも高齢化と健康に対する意識増加で今後10% 近くの伸び率が期待されている。日本でも欧米ほどではないが、緩やかに市場は拡大している。
サプリメントはビタミン、ミネラル、機能性成分を多く摂取できるように錠剤、カプセル、あるいは粉末製品にしたもので、市場には多くの製品がある。日本では日本栄養健康食品協会が機能性成分を製品にしたサプリメントに関する規格を決めている。ビタミン、ミネラル、機能性成分が食品に含まれる量は一般的には少ないし、また偏った食事をして不足していると感じた場合、あるいは特定の症状が起こった時は、サプリメントを利用して十分な量を摂取し欠乏症にならないようにする、あるいは特定の症状の改善をすることができるが、上に述べたように過剰摂取には気をつけなければならない。またサプリメントを処方薬と同時摂取すると、予期せぬ相互作用が起こる場合もある。サプリメントは医薬の代替え品ではなく、天然の原料から作られている食品だから安全であるという保証はない。サプリメントを摂取しすぎて肝臓をこわした人もいる。摂取する前に医師に相談をすることも大事である。最近ではサプリメントを従来の医薬と同じように処方する医師が増えてきている。新しい動きとしては、どのような病気に罹りやすい傾向があるかを遺伝子分析で同定し、個人のニーズにあったサプリメントを調合するサービスを提供するビジネスが始まっている。また腸内菌を分析し、その結果に応じて必要な腸内菌を加えたサプリメントを提供するビジネスもある。サプリメント市場は、アメリカでは成人の70%以上が何らかのサプリメントを摂取しており、大きな市場である。ヨーロッパでも高齢化と健康に対する意識増加で今後10% 近くの伸び率が期待されている。日本でも欧米ほどではないが、緩やかに市場は拡大している。
加工食品と健康
加工食品は現在では多くの人の食事に大きなウエイトを占めており、調理不要ですぐに食べられるようにしたものや、簡単な調理で食べられるようにしたもの、あるいは長持ちするように冷蔵、冷凍された商品など実に様々な商品が販売されている。最近、食品科学界で加工食品の中でも、超あるいは高加工食品が健康によくないという研究が発表されている。この「超あるいは高加工食品」の定義は余り厳密ではないが、加工度の高いもので添加物(特に、塩、砂糖、油脂、保存料、色素)などが多く使われた加工食品とされている。 例えば、ハムやソーセージ、大量生産されたパン、朝食用シリアル、インスタントスープ、冷凍、冷蔵ミール製品、ビスケット、アイスクリーム、フルーツ入りのヨーグルト、炭酸飲料、ウイスキー、ジン、ラムなどのアルコールなどが挙げられている。この分類については現在も議論が継続されているが、最近の多くの研究で、こうした高加工食品をよく食べる人は少ない人に比べて生活習慣病が多く、健康的でないということが示されている。しかしその理由として、高加工食品が直接人を不健康しているのか、高加工食品をよく食べる人は習慣的に健康的な生活をしていない人が多いためなのかは、はっきりしない。今後より厳密な科学的な研究が必要とされている。こうした研究は食品業界にとっては重要である。なぜなら健康に悪いと指摘されると、それら製品の市場が減少する可能性があるからである。
例えば、ハムやソーセージ、大量生産されたパン、朝食用シリアル、インスタントスープ、冷凍、冷蔵ミール製品、ビスケット、アイスクリーム、フルーツ入りのヨーグルト、炭酸飲料、ウイスキー、ジン、ラムなどのアルコールなどが挙げられている。この分類については現在も議論が継続されているが、最近の多くの研究で、こうした高加工食品をよく食べる人は少ない人に比べて生活習慣病が多く、健康的でないということが示されている。しかしその理由として、高加工食品が直接人を不健康しているのか、高加工食品をよく食べる人は習慣的に健康的な生活をしていない人が多いためなのかは、はっきりしない。今後より厳密な科学的な研究が必要とされている。こうした研究は食品業界にとっては重要である。なぜなら健康に悪いと指摘されると、それら製品の市場が減少する可能性があるからである。
加工食品は現在では多くの人の食事に大きなウエイトを占めており、調理不要ですぐに食べられるようにしたものや、簡単な調理で食べられるようにしたもの、あるいは長持ちするように冷蔵、冷凍された商品など実に様々な商品が販売されている。最近、食品科学界で加工食品の中でも、超あるいは高加工食品が健康によくないという研究が発表されている。この「超あるいは高加工食品」の定義は余り厳密ではないが、加工度の高いもので添加物(特に、塩、砂糖、油脂、保存料、色素)などが多く使われた加工食品とされている。
 例えば、ハムやソーセージ、大量生産されたパン、朝食用シリアル、インスタントスープ、冷凍、冷蔵ミール製品、ビスケット、アイスクリーム、フルーツ入りのヨーグルト、炭酸飲料、ウイスキー、ジン、ラムなどのアルコールなどが挙げられている。この分類については現在も議論が継続されているが、最近の多くの研究で、こうした高加工食品をよく食べる人は少ない人に比べて生活習慣病が多く、健康的でないということが示されている。しかしその理由として、高加工食品が直接人を不健康しているのか、高加工食品をよく食べる人は習慣的に健康的な生活をしていない人が多いためなのかは、はっきりしない。今後より厳密な科学的な研究が必要とされている。こうした研究は食品業界にとっては重要である。なぜなら健康に悪いと指摘されると、それら製品の市場が減少する可能性があるからである。
例えば、ハムやソーセージ、大量生産されたパン、朝食用シリアル、インスタントスープ、冷凍、冷蔵ミール製品、ビスケット、アイスクリーム、フルーツ入りのヨーグルト、炭酸飲料、ウイスキー、ジン、ラムなどのアルコールなどが挙げられている。この分類については現在も議論が継続されているが、最近の多くの研究で、こうした高加工食品をよく食べる人は少ない人に比べて生活習慣病が多く、健康的でないということが示されている。しかしその理由として、高加工食品が直接人を不健康しているのか、高加工食品をよく食べる人は習慣的に健康的な生活をしていない人が多いためなのかは、はっきりしない。今後より厳密な科学的な研究が必要とされている。こうした研究は食品業界にとっては重要である。なぜなら健康に悪いと指摘されると、それら製品の市場が減少する可能性があるからである。
健康と食品の関係
人間の身体は食べたもので作られていく。毎日食べている食品が身体の古い組織を新しい組織に戻すために使われている。その機能は年を取るにつれて衰えてくるが、人間の身体は部分にもよるが、3か月から6か月くらいで新しくなっている。それを考えると、何を食べるかが自分の健康を保つのに重要であることが分かる。偏った食事をせずに、できるだけ加工食品を減らし、種々の栄養素が含まれた多くの種類の食品を食べ、食べ過ぎないように適量食べることが健康を保つ秘訣であると筆者は考えている。
人間の身体は食べたもので作られていく。毎日食べている食品が身体の古い組織を新しい組織に戻すために使われている。その機能は年を取るにつれて衰えてくるが、人間の身体は部分にもよるが、3か月から6か月くらいで新しくなっている。それを考えると、何を食べるかが自分の健康を保つのに重要であることが分かる。偏った食事をせずに、できるだけ加工食品を減らし、種々の栄養素が含まれた多くの種類の食品を食べ、食べ過ぎないように適量食べることが健康を保つ秘訣であると筆者は考えている。
これまでこのコラムで健康と食品の関係や多くの商品の紹介などを行ってきたが、今回でこのコラムを終わらせて頂くことになりました。長い間、このコラムを読んでいただいた皆様と、株式会社タバタの皆様に感謝いたします。
©アメリカ食品産業研究会
著者:吉田隆夫プロフィールを見る
著者:吉田隆夫プロフィールを見る