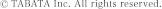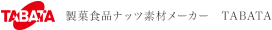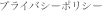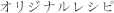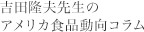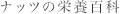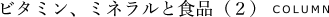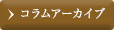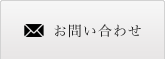まめ知識/まめ知識トップ/ビタミン、ミネラルと食品(2)
2023.03.10
このコラムの前々回にビタミンをテーマにして、健康との関係やビタミンの含まれる製品を具体的に紹介した。1回コラムが飛んだが、今回はミネラルと食品、健康についてまとめてみた。生物の進化の中で、我々人間も自然にあるものを摂取して生命を維持し、さらには身体をより自然に適応させ、より強く、より長く生きるように進化してきた。人間の身体は水を除くと、主に炭素、水素、酸素、窒素からなる有機化合物でできているが、ミネラルも身体に必要な元素である。ミネラルは水を除いて身体の約5-6% を占めている。ミネラルの中で、毎日100mg以上必要となるのは、カルシウム、リン、ナトリウム、塩素,カリウム、硫黄、マグネシウムである。ミネラルには身体の組織を作っているカルシウム、リン、鉄などのミネラルから、代謝機能や酵素反応などに関係し、生命活動を維持しているミネラルに至るまで様々であり、いろいろな形で我々の身体の健康を維持しているのである。
多くのミネラルは1日にどのくらい摂取すれば適切であるかは正確には分かっていないが、1日の推奨摂取量と上限が決められている。アメリカと日本で設定されている摂取量の基準と上限摂取量を表1にまとめてみた。日米ではかなり数値が異なる。カルシウムは女性では日本の推奨摂取量は、アメリカのほぼ半分であるが、これはおそらく日本では魚からカルシウムを日常多く摂取しているからであろう。日本は全体的に少なめであるのは体重などを考慮しているのであろうか。

ナトリウム、カリウム、クロムには上限摂取量が定められていない。しかしながら、余り多く摂取すると異常が起こることは確かである。ここに載せられているミネラルのほとんどは人間の身体の生理作用や代謝で重要な働きをしている。多くのミネラルは微量で機能を発揮している。ミネラルが人の生理機能にどのように関係しているかを簡単にまとめたのが表2である。

ミネラルの摂取量は適切な量でなければならず、不足すると病気になるが、過剰に摂取しても逆に身体の機能のバランスを崩し、病気になる。また、水銀(有機水銀)やカドミウム、鉛などのミネラルは微量でも身体に入ると病気が起こるので、食品だけでなく環境汚染でも厳しくコントロールされている。ミネラルについて、欠乏による疾病および過剰摂取による障害は表3にリストされている。ミネラルは身体の代謝やその他の機能に重要な働きをしているものが多いが、バナジウム、ボロンなどのように人間の生理機能に必要かどうかが分かっていないミネラルもある。食品から十分摂取出来ており、むしろ過剰摂取に気をつけなければならないミネラルはナトリウムとリンである。不足しがちなミネラルはカルシウム、鉄、マグネシウム、カリウム、亜鉛などである。ミネラルはごく少量の摂取で充分であるので、それらが含まれている食品を摂取することが大事である。こうしたミネラルの欠乏あるいは過剰摂取で病気が起こるのであるが、中でも女性のカルシウム摂取不足による骨そしょう症や鉄分不足による貧血、さらには亜鉛不足による味覚障害などはよく知られている。サプリメントから摂取する場合は、医者と相談してから摂取する方が望ましい。医者は症状の観察と、食事の内容を聞いてミネラルの摂取が十分であるかどうかを判断する。普段、我々消費者は余りミネラルについては、関心を向けないのが普通である。それはカルシウムやナトリウム以外のミネラルは普通に食事を摂取していれば問題は起こらないからである。

ほとんどの食品には、ミネラルが含まれているが、特にどのような食品に多く含まれているのであろうか。食品のカテゴリーで多く含まれているミネラルを表4にリストしてみた。食品からミネラルを摂取する際は、できるだけ多くの種類の食品を摂取することで、幅広い種類のミネラルを摂取するよう心掛けたい。

 ミネラルの摂取が不足している場合は、サプリメントなどから摂取することができるが、医師と相談して摂取しすぎないようにしなければならない。サプリメントでは多くの量を摂取しなければならないカルシウムや、不足がちになるマグネシウム、亜鉛、鉄分、カリウムなどの単体での製品がある。さらに、種々のミネラルの混合したマルチ・ミネラル製品があり、例として3製品(写真1)を取り上げた(DV は1日の推奨摂取量)。“Full Spectrum Mineral Caps” は、カルシウム(DV 19%)、ヨウ素(ヨウ化カリウムとして)(DV 75%)、マグネシウム (DV 60%)、亜鉛 (DV 68%)、セレン (DV 91%)、銅 (DV 111%)、マンガン (DV 109%)、クロム (DV 286%)、モリブデン (DV 111%)、カリウム (DV 1%)がビタミンD3 (DV 25%) と一緒にカプセル化されている。これは骨の健康を中心として、亜鉛による免疫性維持などを目的としたサプリメントである。 “Only Trace Minerals” は、亜鉛 (DV 182%)、銅 (DV 222%)、マンガン (DV 87%)、クロム (DV 1143%)、モリブデン (DV 556%)、ボロン (3mg)、バナジウム(3.75mg) を処方している。この製品は亜鉛の免疫性維持を中心に、一般的な健康を維持することを目的としている。しかし、銅、クロム、モリブデンなどは1日推奨摂取量よりもかなり多く入っているので注意して摂取する必要がある。 “Multi Minerals” は、カルシウム (DV 12%)、鉄 (DV 75%)、ヨウ素 (DV 170%)、マグネシウム (DV 36%)、亜鉛 (DV 75%)、セレン (DV 75%)、銅 (DV 75%)、マンガン (DV 75%)、クロム (75%)、モリブデン (DV 75%)、カリウム (DV 1%)に、L-グルタミン、ボロン (0.75mg)、バナジウム (75mg) を加えている。この製品は1日推奨摂取量よりも低い量で処方を作っているので、より安全であると考えられる。このミネラル剤は代謝と細胞の健康を保つことをその利用目的としている。こうしたサプリメントは菜食主義者や偏った食事をする人には必要であるかも知れないが、普通にバランスの取れた食事をしていれば、こうしたサプリメントは必要がない。ミネラルは我々の健康に必須のものであるので、食品にどのようなミネラルが含まれているかを知ることも大事である。
ミネラルの摂取が不足している場合は、サプリメントなどから摂取することができるが、医師と相談して摂取しすぎないようにしなければならない。サプリメントでは多くの量を摂取しなければならないカルシウムや、不足がちになるマグネシウム、亜鉛、鉄分、カリウムなどの単体での製品がある。さらに、種々のミネラルの混合したマルチ・ミネラル製品があり、例として3製品(写真1)を取り上げた(DV は1日の推奨摂取量)。“Full Spectrum Mineral Caps” は、カルシウム(DV 19%)、ヨウ素(ヨウ化カリウムとして)(DV 75%)、マグネシウム (DV 60%)、亜鉛 (DV 68%)、セレン (DV 91%)、銅 (DV 111%)、マンガン (DV 109%)、クロム (DV 286%)、モリブデン (DV 111%)、カリウム (DV 1%)がビタミンD3 (DV 25%) と一緒にカプセル化されている。これは骨の健康を中心として、亜鉛による免疫性維持などを目的としたサプリメントである。 “Only Trace Minerals” は、亜鉛 (DV 182%)、銅 (DV 222%)、マンガン (DV 87%)、クロム (DV 1143%)、モリブデン (DV 556%)、ボロン (3mg)、バナジウム(3.75mg) を処方している。この製品は亜鉛の免疫性維持を中心に、一般的な健康を維持することを目的としている。しかし、銅、クロム、モリブデンなどは1日推奨摂取量よりもかなり多く入っているので注意して摂取する必要がある。 “Multi Minerals” は、カルシウム (DV 12%)、鉄 (DV 75%)、ヨウ素 (DV 170%)、マグネシウム (DV 36%)、亜鉛 (DV 75%)、セレン (DV 75%)、銅 (DV 75%)、マンガン (DV 75%)、クロム (75%)、モリブデン (DV 75%)、カリウム (DV 1%)に、L-グルタミン、ボロン (0.75mg)、バナジウム (75mg) を加えている。この製品は1日推奨摂取量よりも低い量で処方を作っているので、より安全であると考えられる。このミネラル剤は代謝と細胞の健康を保つことをその利用目的としている。こうしたサプリメントは菜食主義者や偏った食事をする人には必要であるかも知れないが、普通にバランスの取れた食事をしていれば、こうしたサプリメントは必要がない。ミネラルは我々の健康に必須のものであるので、食品にどのようなミネラルが含まれているかを知ることも大事である。
©アメリカ食品産業研究会
著者:吉田隆夫プロフィールを見る
著者:吉田隆夫プロフィールを見る